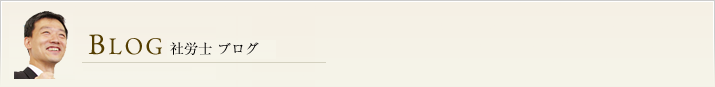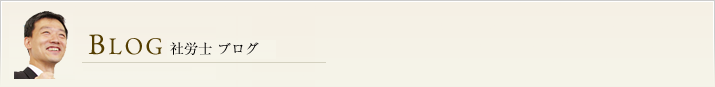
令和7年度最新 助成金活用セミナー
2025年4月8日 火曜日
企業にとって”得しかない”助成金をご存じですか?
助成金は「返済不要」で要件さえ満たしていたらどの企業でも需給ができるものです
が、「助成金を知っているかどうか」と「要件を満たせるか」が受給の分かれ道になり
ます。
令和 7 年度において助成金活用を検討している経営者は、どの助成金を申請できるか
情報を仕入れることが大切です。
本セミナーでは、令和 7 年度最新助成金情報を助成金の専門家が解説します!
助成金情報だけではなく、「要件を満たすためのポイント」や「受給に向けた準備」に
ついて詳しくご案内します
1つでも当てはまる方は是非ご参加ください!
・直近で従業員の採用を考えている
・パパ育休や介護休業を取得する予定の従業員がいる
・従業員の賃金アップや待遇改善を実施したいと思っている
・導入したい設備やシステムがあるが資金不足で悩んでいる
・60 歳以上の被保険者である従業員がいる

■開催日
4 月 24 日(木)14 時~15 時
■講師
ひかり社会保険労務士法人 代表社員 徳光 耕嗣
■費用
無料
■参加特典
助成金の専門家の社労士による助成金に関する無料個別相談(30分)
助成金を受給するための要件を満たしているか確認し受給のためのアドバイスをします!
■助成金無料診断
受給可能性のある助成金の見込額を可視化する助成金受給診断を無料で実施します!
■セミナーお申込み方法
https://forms.gle/aQL1eNy2tngcff9GA
上記 URL よりお申込みください。皆様のご参加をお待ちしております。
令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法に向けて
2025年3月26日 水曜日
令和7年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正は、企業にとって無視できない内容を多く含んでおり、制度面・実務面の両面で大きな影響があるといえます。さらに10月にも改正が予定されており、今後も関連法令のアップデートには注意が必要です。
当法人では、現在、顧問先企業様からのご依頼を受けて、改正に対応した育児・介護休業規程の改定作業を進めています。その中で「せっかくの機会なので他の就業規則も見直したい」「以前から気になっていた箇所をこのタイミングで修正したい」といったお声もいただいています。
就業規則は、言うなれば会社のルールブック。従業員との信頼関係を築き、日々の労務管理を円滑に進めるうえでの土台となるものです。だからこそ、あいまいな表現や実態にそぐわないルールが記載されていると、ちょっとした誤解がトラブルの火種になることも少なくありません。
法改正に対応するための規程改定はもちろんのこと、これを機に就業規則全体の表現や構成を見直すことも、トラブル予防や社内の運用の見直しにつながる良い機会です。当法人でも、企業ごとの実情に合わせて、丁寧にヒアリングを行いながら慎重に改訂を進めています。
2月を終えて
2025年3月3日 月曜日
こんにちは。ひかり社労士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。
2月も終わり、年明けからあっという間の2ヶ月でした。
2月は今季一番の大寒波が襲来し、通勤や業務にも影響があったかと思いますが、顧問先様からもご相談をいただきました。
「雪のため業務ができず休業するのですが休業手当の支給は必要でしょうか?」
労働基準法第26条において、「使用者の責に帰すべき事由」によって、労働者を休業させた場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないとされていますが、休業が使用者の責ではなく不可抗力による場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。大雪によって事業場の施設・設備が直接被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、不可抗力に当たりますので、休業手当の支払の対象にはなりません。ただし、大雪による直接的な被害を受けていない場合には「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられるケースもあります。
日本は地震、台風や雪など自然災害の影響を受けやすいため、ケースによって不可抗力による休業であるのか判断が必要となります。ふと疑問に思われたり、判断に迷われた際はお気軽にご相談ください。
業務の効率化について
2025年2月28日 金曜日
当法人では、今年度からの取り組みとして、業務の効率化を図るため「PADチーム」を発足し、MicrosoftのPower Automate for Desktop(通称PAD)を活用した業務の自動化を進めています。
PADとは、Microsoftが提供するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールの一つで、繰り返し発生する業務を自動化できる便利なツールです。
マウス操作やキーボード入力などの動作を記録し、プログラミングの知識がなくても、Excelやブラウザ操作、ファイル管理などの一連の作業をボタン一つで再現できるのが特徴です。
現在、データのダウンロードや公文書の保存作業などの業務を順次PADに置き換えています。
単純な繰り返し作業を自動化することで時間短縮につながり、業務負担の軽減が進み、空いた時間をより重要な業務へ活用できるよう努めています。
すべての作業を機械に任せることはできないため、申請書類の確認や重要なデータのチェックなど、人の目で確認すべき部分は慎重な対応が必要ですが、効率化を進めることで、より多くの時間を本来注力すべき業務に充てられるようになり、質の向上にもつながると考えています。
業務の効率化は一朝一夕には進むものではないですが、今後も改善を重ねることで、より良いサービスにつなげていくことを目指していきます。
当法人の取り組みについては、今後もブログを通じて発信してまいります。
ひかりアドバイザーグループ職員会議
2025年1月31日 金曜日
新年を迎えてから早くも1カ月が過ぎようとしています。新年の目標に向かって歩み始めた方も多いと思います。
今回は当法人のグループの話です。
先日、グループ法人全体での職員会議が開かれました。
これは半年に1回、各士業法人の職員が集まり、法人代表の方針発表会や懇親会が行われるものです。
期首に他法人の方針や意気込みを聴けること、日頃メールや電話のやり取りのみの他法人の職員と直接話せることは、貴重な機会です。
今回の職員会議では、各法人間のパネルディスカッションが行われました。
テーマはいくつかありましたが、AIと今後の士業の業務についてのディスカッションは興味深かったです。
AIに仕事を奪われるというネガティブなイメージが多い中、そこをチャンスと捉えるという意見は、当法人で昨年から取り組んでいる業務の効率化や付加価値の提供に通じるものがあります。
昨年からチームでの取組みが始まり、なかなか思うように進まないこともありますが、年初に前向きな話を聞くことで、次の半年に向けてまた根気強く進めていこうと気持ちを新たにしました。